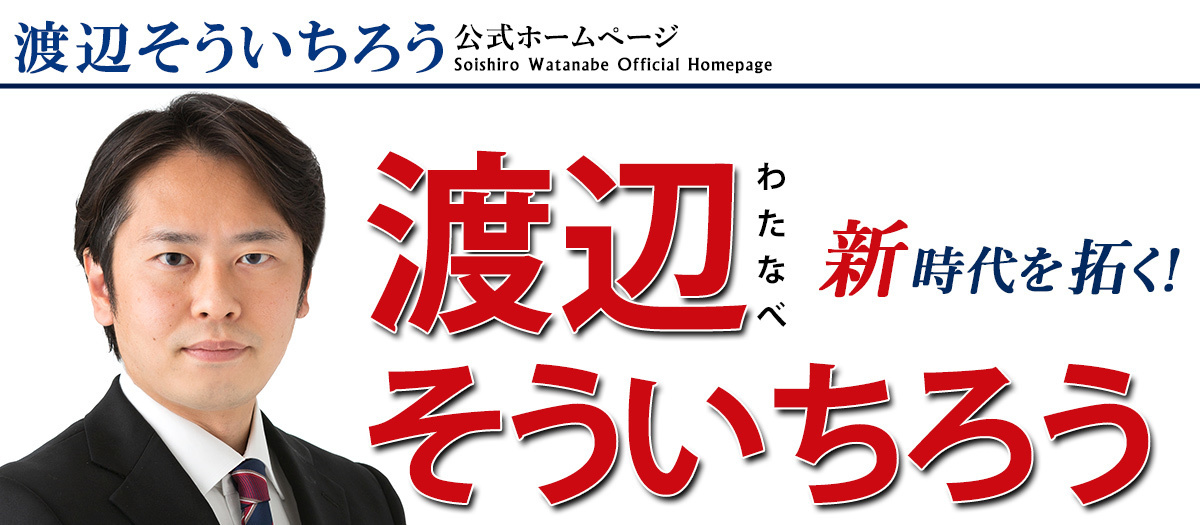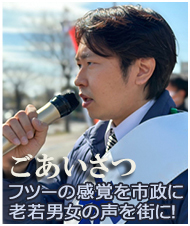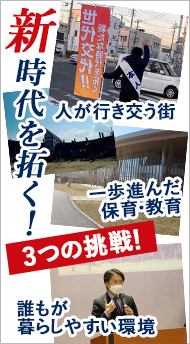白岡の子育て支援① (12月議会一般質問)
「待機児童の数は把握できない?」
今年、白岡市では「保育園を増やしたのに待機児童が増える」という不思議な事態が起こりました。
2015年の時点で白岡には13人の待機児童がいました。そこで待機児童解消を図るために、新たに90名が入所できる保育園がオープンしました。すると、今度はその保育園がすぐに定員オーバーになり、待機児童は18人に増えました。

本来なら解消されるはずの待機児童が逆に増える。まずこの理由のひとつは待機児童数のカウント方式が、実際に保育所の入所を断られた方の人数ではないため、数字の裏に隠れた多くの待機児童がいる事。そしてもうひとつの理由は、新しい保育所ができたことによって潜在的な保育ニーズが掘り起こされたためです。
子育て世帯の方々の中には「自分で子育てをしているけれど、もし新しい保育所ができたなら、私も子どもを預けて働きたい」と考える方も多く、待機児童は状況によって増える可能性があります。つまり待機児童問題は、需要が供給を生むだけでなく、供給が需要を生む構造にもなっていると考えられます。
こういった「いたちごっこ」のような現象は潜在的な保育ニーズを把握しない限り続きます。待機児童対策には、まず自治体による正確できめ細かな情報把握が必要です。そこで以下を質問しました。
Q渡辺:これから保育所を整備する上でも、市内の潜在的な保育ニーズを把握していくことが必要ではないか。白岡で生まれる子供の数は毎年400人規模で、親御さんと接触する機会もいくつかある。その際に例えばアンケートなどを行い、より確かな保育ニーズを把握できないか?
A子育て支援課:潜在的な保育ニーズの把握は極めて難しい。社会状況や景気の動向によっても保育需要は変化すると考えている。現在、待機児童の人数ではなく、実際に保育所に入所できなかった方の人数をもとに、需要と供給の見直しを行っている。保育所の申し込み人数を見ながら、現状把握に努めたい。

「アフターフォローの取り組みは?」
Q渡辺:是非、できる限り正確な情報把握を行ってほしい。また実際に保育所に入所できなかった方に対しては、アフターフォローや代替サービスの情報提供が必要だが、どのような取り組みを行っているか?やむなく入所を断った場合には、その後のきめ細かなフォローが大切だが?
A子育て支援課:保育所の入所をお断りした方には、認可外保育所やファミリーサポートセンター、民間保育園の一時保育の利用を案内している。また、保育所に空きが生じた場合には、随時、保育を必要とする優先度の高い方から順番に入所案内を行い、情報提供に努めている。