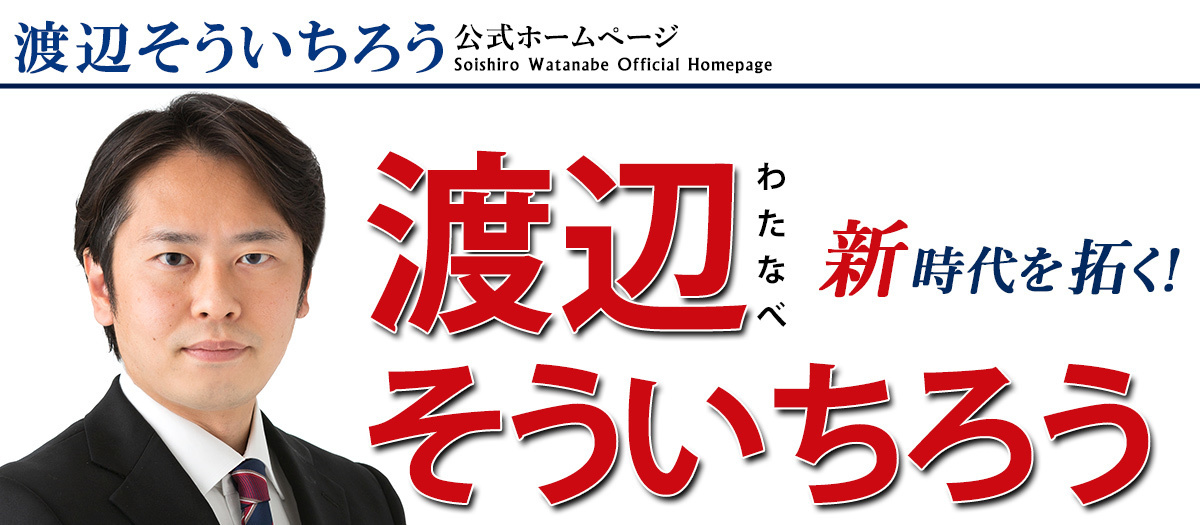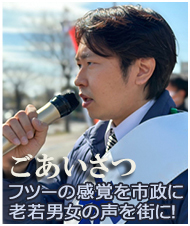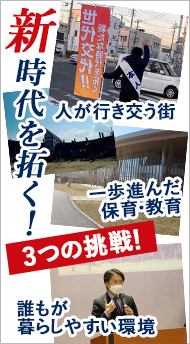願いを込めたスカイランタン 2026/2/1
「夜空に願いを スカイランタン」が白岡市総合運動公園で開催されました。スカイランタンを夜空に広げるチャリティーイベントで、白岡市役所の火災がきっかけで企画されました。イベントの収益は白岡市役所復旧の費用に充てられます。

17時ごろに一斉にランタンを空に飛ばしました。ランタンが空に浮かぶと会場は幻想的であたたかい雰囲気に。3歳の娘も「ラプンツェルみたい!」と大喜び。良い思い出になったのでは。


開催にあたっては様々なハードルもあったと思いますが、大成功だったと思います。主催されたまちカケル想いの皆様、関係の皆様、ありがとうございました。