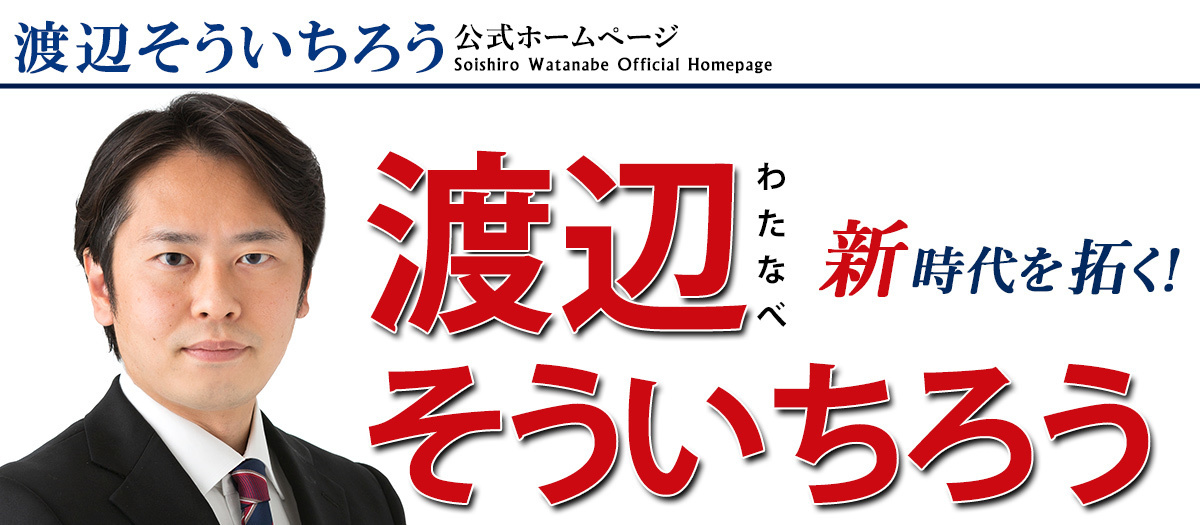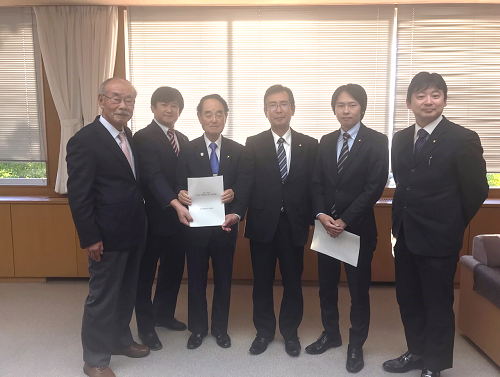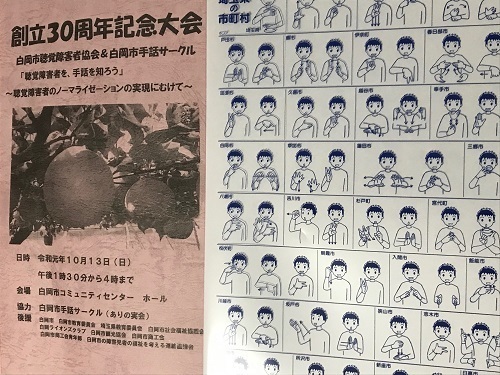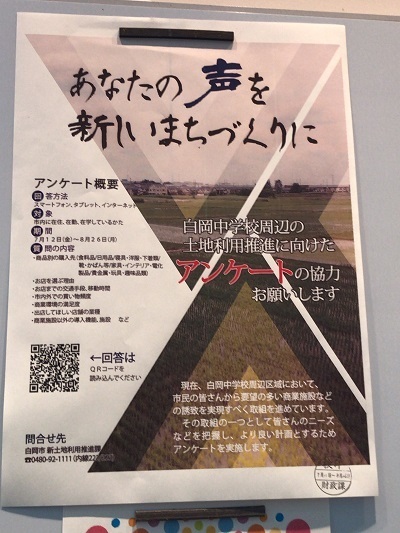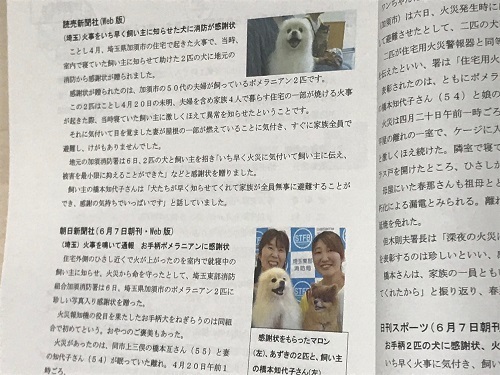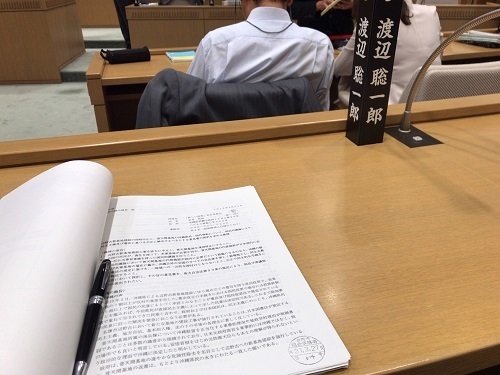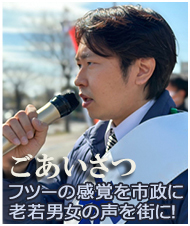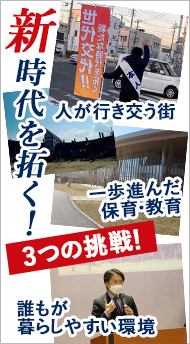新たな門出の言祝ぎ 2020/1/12(日)

白岡では成人の日から一日早く成人式が行われました。
白岡の成人式は生涯学習センタ−「こもれびの森」にて挙行されます。今年は500名を超える方が成人を迎えました。こもれびの森いっぱいに新成人と保護者の方々が集まりました。市長らが祝辞を述べ、その後学生時代の恩師による激励がありました。終始、温かい雰囲気の中で行われた成人式でした。
新成人の皆様には新たなスタートの日です。大人になると、これまでより自由度が拡大します。それと同時に責任は重くなります。自立した社会人としての自覚をもって、大きく拡がっていく自らの人生を楽しんで頂きたいと思います。
色々な事に挑戦して、どんどん新しい価値を創造していってください。
新成人の皆様、本日は誠におめでとうございます。皆様の輝かしい前途をお祈りいたします。