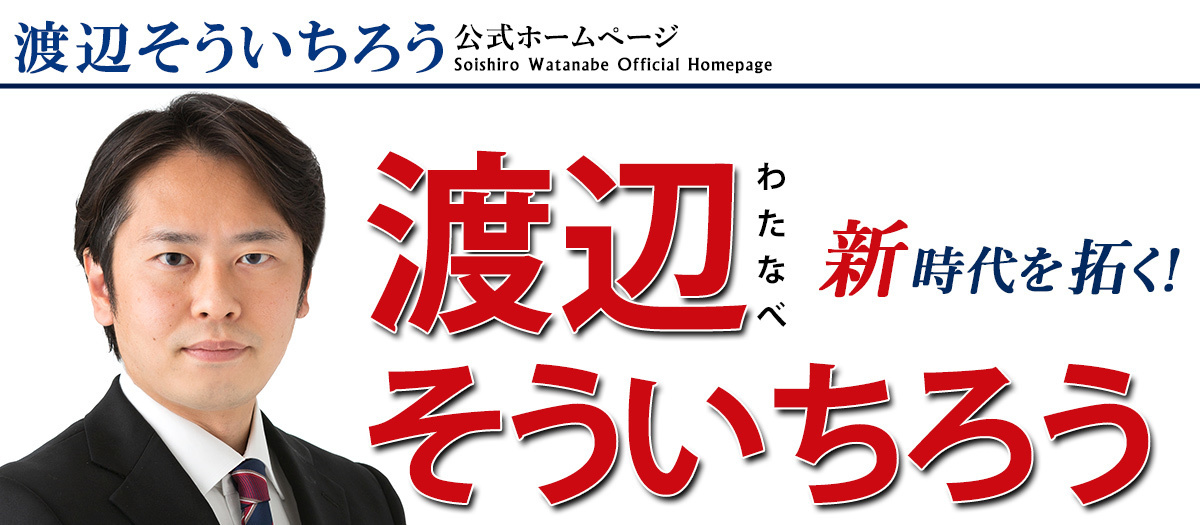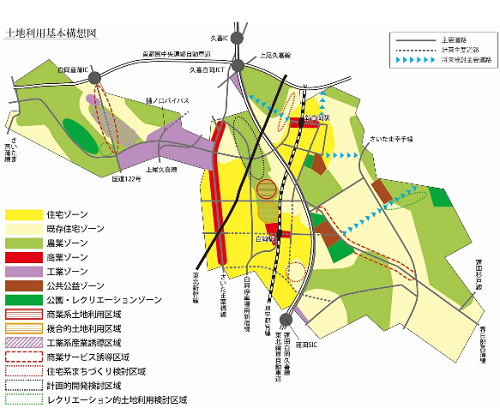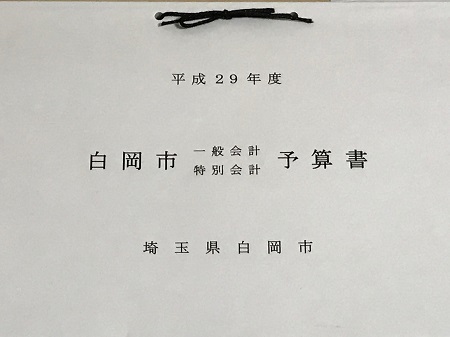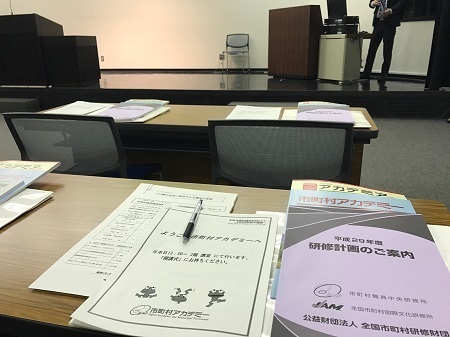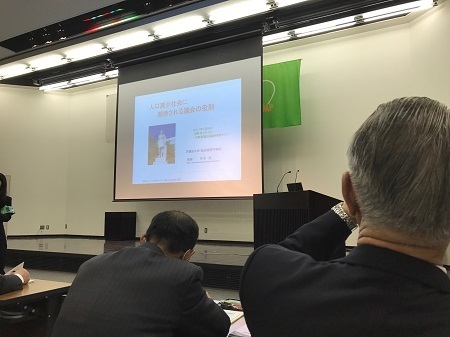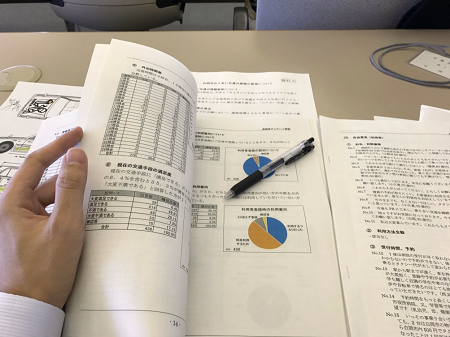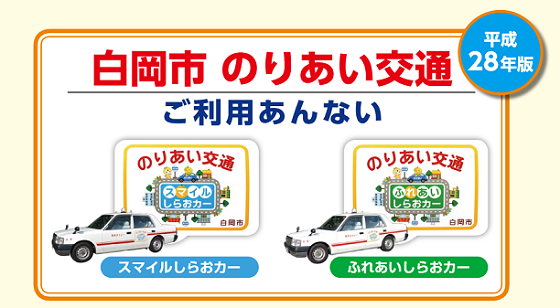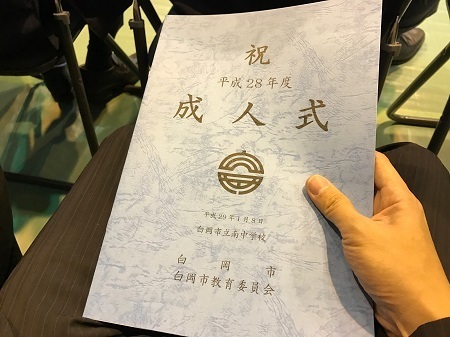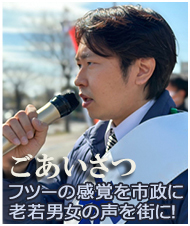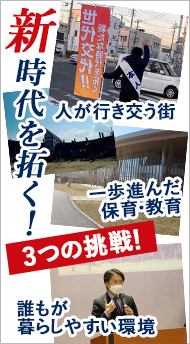講義を行う方は中西寛氏など著名な方々です。地方自治から国際政治まで幅広く講義がありました。情報としては既知のものが多かったですが、改めて考えるきっかけを頂いた講義もありためになる内容でした。
最初の講義は「人口減少時代の議会の役割について」。議員はより市民に近い存在になる必要性があり、女性や若者など多様な意思を議会に反映させる必要がある、とのこと。また人口が減っていく中で、スマートシュリンク(まち全体のコンパクト化)を目指して公共施設の統廃合など都市の再改造が必要という内容でした。
次に「観光政策について」。LCCの存在やアジアの発展でインバウンドは今後も伸びると考えられる。日本はさらに観光政策に力を入れていく意味がある。特に地方は今ある資源を見直して新たな価値を創れ、という内容でした。講師は韓国の方で、海外から見た日本と日本の地方の魅力について話がありました。情熱的で面白い内容の講演でした。中でも日本人の技術伝承(匠の精神と言っていました。)は外国人が評価する日本の大きな価値だとおっしゃっていたのが印象に残りました。
2日目の講義は「国際政治について」。トランプ政権の外交戦略と日本政治の今後について話がありました。主にアメリカ外交の今後について国際情勢から読み解く内容でした。また日本の国内政治については、現状、安倍政権に代替できる力を持つ政治勢力は自民党内にも他党にも無いが、アベノミクスに対する地方レベルの不満が結びつけば、新たな地方政治の潮流(小池さんや橋下さんのような)が代替的なものに成長する可能性がある。という話がありました。
最後は「資本主義と経済格差について」。一握りの富裕層に富が偏在している格差の問題など資本主義が行き詰まりを迎えているという話。ピケティが提案する富裕税や資産への累進課税など、富の再分配と格差の是正について政治は責任を持たなければならないという内容でした。1%の超富裕層の資産の方が、残る99%の人々の資産すべての合計よりも多いという推計もあるようですが、こういった経済格差については、日本だけでなく、それこそグローバルな枠組みでの取り組みを考えていく必要があると思いました。
講義の他には、全国の議員さんとの意見交換会もありました。宮城や岩手の議員の方から東北の現状や課題についてお話しを聞くことができました。北海道など遠方からきている議員の方とは農産物のブランド化の話で盛り上がりました。
白岡市と共通の課題について意見交換もできて非常に有意義でした。今後の活動で活かしていきたいと思います。