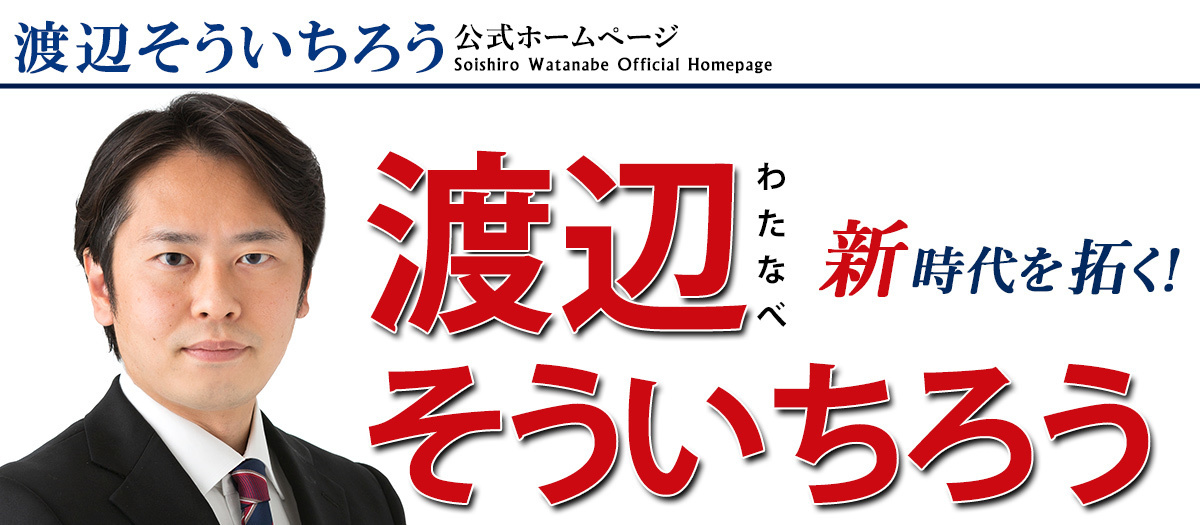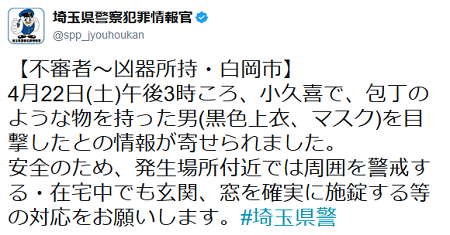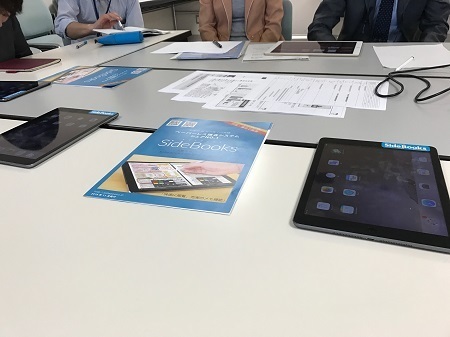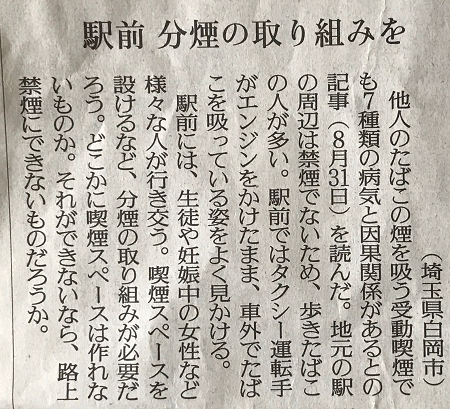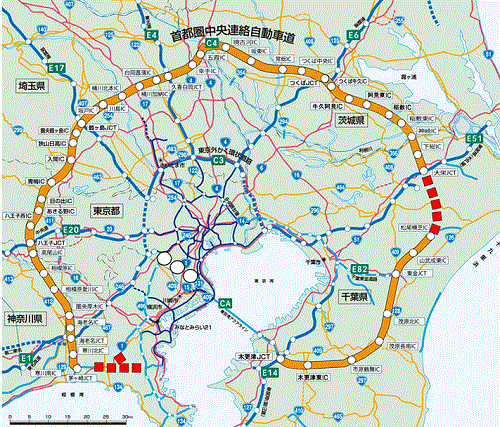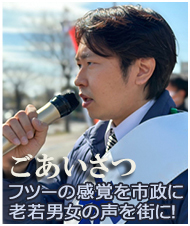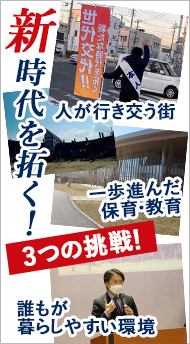消防局へ 2017/5/9(火)
今日は総務委員会の活動で東部消防組合消防局に行きました。近年の火災や消防活動の状況を伺いました。白岡市は久喜市、加須市、幸手市、宮代町、杉戸町の4市2町で広域消防を構成しています。本部は久喜にあり、645名の職員が働いています。
白岡市では火災は年々減っていますが、救急車の出動回数は増えています。高齢化の影響もあって救急需要は全国的に高まっています。

消防局では普段から様々な災害を想定した訓練が行われています。119番通報から救急隊出動までの情報システムや、新たに導入された災害用支援車を見せて頂きました。ドローン等も配備され非常に充実した装備になっています。